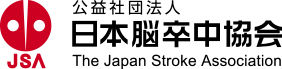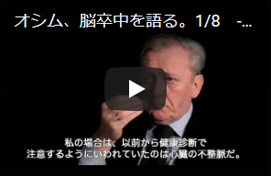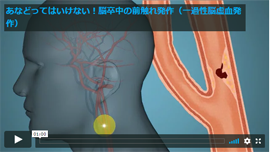脳卒中の原因となる生活習慣や病気を知って予防することが大切です。
そして万が一のために脳卒中の症状を知り、脳卒中かな?と思った時はすぐ救急車を呼ぶことが、後遺症を軽くして人生を救うことにつながります。
厚生労働省2021年度「循環器病に関する普及 啓発事業委託費」によって制作
もう少し詳しく漫画で読んでみよう
著作物使用許諾及び著作権に関わるお申し込みやお問い合わせは お問い合わせフォーム へお願いします
著作物使用許諾及び著作権に関わるお申し込みやお問い合わせは お問い合わせフォーム へお願いします
ダウンロードして読んでみよう
イラストをクリックすると閲覧できます(外部サイトに移動)。
拡大して見ることもできます。
ダウンロードデータを私的利用以外でお使いになる時はお問い合わせフォームにご連絡ください。
著作物使用許諾及び著作権に関わるお申し込みやお問い合わせは お問い合わせフォーム へお願いします
冊子を読んで脳卒中を学ぼう
ご入会いただいた方には無料で1冊ずつお届けします。
 |
1.脳卒中を予防するための十か条脳卒中予防十か条を解説した小冊子です。脳卒中とはどんな病気なのか、最近の傾向とともに解説されています。 提供:ファイザー |
 |
2.脳卒中の克服に向けた十か条脳卒中は予防のみならず、発症後は、再発予防のための“治療の継続”と“リハビリテーションの継続”も重要です。そこでこの度、脳卒中後も再発を防いで活き活きした人生を送るための「脳卒中克服十か条」を作成しました。 提供:ファイザー |
 |
3.ドキドキしたら、脈を確かめましょう「心房細動」は重い脳梗塞の原因となります。心房細動によりできた血のかたまり(血栓)が脳に運ばれ、血管を詰まらせやすいためです。 提供:日本べーリンガーインゲルハイム |
 |
4. よくわかる脳卒中脳卒中の予防方法、治療やリハビリテーション、暮らしについて書かれた冊子です。 監修:日本脳卒中協会 |
 |
5. いきなりやってくる脳卒中に気をつけて!!
|
冊子取り寄せ方法
ご希望の皆さまには送料をご負担いただいております。 送料は予め事務局にお問い合わせください。冊子本体は無料です。 冊子は在庫がなくなり次第、配布を終了いたします。
- 申し込み先
冊子名、希望数、送り先(郵便番号、住所、氏名)を明記の上、送料(郵便切手)を同封してお申し込みください。冊数によっては送料着払いとさせていただきます。
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-15 共同ビル4階 日本脳卒中協会 - お問い合せ先
日本脳卒中協会 事務局:問い合わせフォーム